病をみて、患者をみて、地域をみる
インタビュー先の事業所とご担当者様

診療同行看護師と訪問看護師とで求められる役割の違い

こちらこそ、よろしくお願い致します。

まず、こちらのグループでは「在宅医療」「地域支援」に関わる多様な働き方の用意をされていることに驚きました。
同グループで「クリニック」を持って、「看多機」を運営して、「就労支援」までされているところは、私が知る限り他の法人では思いつかないかな…と。

こちらの法人に転職希望をされる方は、
「往診の様子を学びたい」
「訪問看護をやりたい」
「看多機で働いてみたい」
といった感じで、自身で働き方の希望を持って入職される方が多いのですか?

う~~~ん、どうですかね……。
自分が「訪問看護を!」と言って入職をされた方が、色々と話してみると「訪問診療の方が合っているよね」と変わるケースもありますし、その逆のパターンもあります。
そういった意味では、うちの理念や事業に興味を持って頂けたら、働き方についてはまずは相談をして頂くのが双方にとって良いのかなと思います。

なるほど…!
ちなみに、在宅に興味のある看護師さんとお話をしていて、訪問看護については実習での現場体験をされている方は多いのですが、往診同行については現場のイメージがついていないという方が多いかと感じています。
「往診同行では訪問看護とこんな点が違う」といったポイントは何かございますか?

こういった言い方は個人的にはあまり好きじゃないのですが、
現在の医療体制って医師がトップに立ち、医師の指示のもとに動いていく、といった仕組みになっているじゃないですか?
そういう意味で、在宅医療においても往診や訪問診療をする医師が、何を考えて、どういう意図をもって指示を出しているのか、といった点に一定の理解は必要になってくるんですね。

そこの理解や肌感覚のようなものを学んでいくのには、訪問看護よりも往診同行の方が得やすいかと思っています。
医師側の目線としては、訪問看護との意思疎通で難しさを感じる場面はありますし、訪問看護側としても医師の判断の意図が組みづらい場面はあるのかなと。

こちらの事業所では、医師、往診同行看護師、訪問看護師をワンフロアで配置しているのは、そこの意思疎通をスムーズにする意図があってのものなのですか??

まさにそうです!
そこは事業所をデザインするうえで、僕が最もこだわったポイントでした。
診療・訪看・リハがワンフロアで働いていて、患者さんに関する議論やカンファレンスが自由にできるようになっています。
以前はここにケアマネも入れていたのですが、そこはフロアのキャパシティの関係で移動になってしまい…(汗)。

先程の職種間での意思疎通の壁の話じゃないですが、僕(医師)が間に入らなくても、診療同行の看護師と訪問看護師とで情報共有ができると現場がスムーズに回るようになるんですよね。
訪問看護師側からしても、医師にダイレクトに伝えるより、同じ看護師同士でコミュニケーションを取った方が伝わりやすいことも結構あるのかなと。

その感覚はあるでしょうね。
まとめると、医師と患者さんとの架け橋として看護師が存在した際に、一歩、医師側(医療面)に立つのが診療同行の看護師で、患者さん側(生活面)に立つのが訪問看護師ってイメージで良いですかね?

はい、そのような感じですね!

良い在宅医ってどんな医者?

先程の診療同行看護師についてですが、僕ら在宅医の学会とかでもよく話題に挙がる議題なんです。
「(往診・訪問診療は)誰と一緒にまわるべきなのか?」と。

往診クリニックの中には、看護師ではなく、専属のアシスタント職を用意しているところや、事務さんが同行するところもありますよね。

そうですね。
うちは患者さんがガン末期の方など医療処置の必要な方が多い、といった前提条件もあるのですが、看護師の同行にはこだわっていきたいなと考えています。

理由はいくつもあるのですが、在宅医療をしていくうえで、患者さんの生活面での気付きってすごく大切なのですが、医師ってそういった点には疎いことが多くって…(汗)。
いわゆる「治療」「診療」といった医療的な部分以外の「生活」「環境」といった点においては看護師に大きく担ってもらっています。

なにか「看護師ならではの視点に助けられた」といった一例はありますか??

たくさんありますよ!
例えば、ある糖尿病の女性の患者さんに訪問に入るようになり、容態がすごく良くなっていったはずの方が、途中からまたどんどん悪化していって「なんでだろう?」と原因がわからなかったんですね。
ご主人に話をきいてみると「食事も普通に茶碗1杯ですし…」と言うんです。
すると、うちの看護師が「お父さん、茶碗みせて」と言って、持ってきてもらった茶碗が大きな丼ぶりで…(苦笑)。

それは茶碗とは言わない(笑)。

そうそう(笑)。
つまりは、食べてるご飯の量が多すぎたんです。
これは自分ひとりだったらまず気づかなかったですね。
「もし自分だったら薬を増やして終わっていたろうな」「こういった気付きを持てるのは看護師の持つ力だな」と、すごく関心したことを覚えています。


もともと、僕のもつ医療チームの思想としては、
医師も看護師も他のコメディカルも、各職種が全部フラットな平面の上に存在していて、ただ1人、コーディネーター役が全体を俯瞰して適切な指示を出す形が良い
と思っています。

現在の日本の医療制度ですと、そのコーディネーター=医師といった図式になっていますが、そこは必ずしも医師である必要はないと?

そう思います。
なぜなら医師の能力や専門性にも限界があるからです。
今でもよく覚えているのですが、僕が医師国家試験を受けた頃、昭和の戦後直後の国家試験が始まった時と比べて知識量として500倍近く要求されるようになっていると教えられました。
僕の時代でそうなのですから、現在の医師は、その当時と比べてもさらに何倍も何十倍もの知識が求められていると思います。
それだけ細分化・高度化した膨大な情報量と向き合っていく中で、1人の医師が神のように全てを把握して指示していくことは無理があるんです。

なので、医師は医療面に集中する必要がありますし、看護師をはじめとしたそれ以外の職種も、それぞれの専門性に沿ったパーツを担っていくしかないんですね。
ただ、誰かが全体像を把握してコントロールをしないとグチャグチャになってしまうので、そこのコーディネート役も1人は必要となる。

制度上は医師が指示出しをする役割ですので、コーディネート役に近くはなりますが、特段、医師がコーディネート教育を受けている訳ではないですし、職種としての専門性もそこではないのかな?といった感じがしますね。

おっしゃる通りです。
だから、コーディネート能力が高い方で、かつ、医師や看護師とのコミュニケーションが取れる方であれば、極端な話、有資格者でなくても良いんじゃないかな?と個人的には思っています。

なるほど……!
少し話は変わるのですが、鈴木先生の考える「良い在宅医」ってどんな医師をイメージされますか?

う~~~~ん、難しい質問ですね……(汗)。
よく言われるのは「患者さんの話をよく聴いてくれる」とか挙げられるのですが、それがイコールで「良い在宅医」の要件かと言うと、若干の違和感はあるんですよね…。

一例として、うちのクリニックが開業したての時に、患者さんやケアマネに対してアンケートを取ったことがあるんですね。
「在宅医療(在宅クリニック)にどのようなことを求めますか?」と。

アンケート項目には、例えば、
・専門性を持って難しい治療ができる
・色々な科の先生が所属している
とかとか、色々な項目を入れたのですが、結果としてはある回答が圧倒的に多かったんです。

なんですか???

「(何かあった時に)すぐに駆けつけてくれる」
という回答ですね。
僕らに求められているのは大学病院や専門病院のような高度医療ではなく、24時間365日対応をしてくれるコンビニエンスストアのような利便性と手軽さ(フットワークの軽さ)だったんです。

おっしゃることはすごくわかるのですが、その言葉に抵抗感をもつ在宅の先生は多そうですね…(汗)。

そうですよね(苦笑)。

勤務医として感じた病院の限界とその先の世界へ

ここからは鈴木先生のご経歴についてお伺いをしていきたいと思います。
ご出身はこの辺だったのですか??

いえいえ、出身は神奈川県の藤沢市なんです。

藤沢市って在宅医療が盛んなエリアですよね!

それは藤沢の南の方ですね。
北の方はまだまだ在宅は弱いんですよ。
めちゃくちゃ田舎!ってことはないのですが、そんなに栄えている地域でもなくって…。

そうなのですね!
ちなみに、お母さまも医師で、往診をされていたとか?

そうです。
母は、基本は外来で、プラスで往診も少しやっているという感じでした。

鈴木先生が在宅医療を意識されたのはお母さまの影響もありましたか?

あったと思います。
ただ、僕の場合は「在宅医療」単体よりも「地域全体のヘルスケア」に関心を持っていたので、そこは母とは違う点でしたね。

「地域」に関心を持たれたのは何かキッカケがあったのですか?

はい。
もう20年近く前なのですが、病院で消化器外科医をやっていたときに、施設に入居中の患者さんで嚥下障害のある方の胃ろうの造設をしました。
胃ろうのメリット・デメリットも、リスクについてもしっかりと話し合ったうえで進めたのですが、
退院して程なくして、担当した施設のワーカーが「胃ろうの使い方がわからない」と言ってご飯を食べさせてしまい、それが原因で肺炎となり、結果2週間ほどで亡くなってしまいました。

それがすごく無力感を覚えた原体験でした…。
おこがましい言い方ですが、自分ひとりが病院の中で頑張ったところで、結果的にその方の人生を救っていくことはできないんだなと。

大なり小なり、同様のことは日本中の各地で起きていそうですね…。
その後は、病院を退職されたのですか?

そうですね。
最初は厚労省に入って世の中を変える仕組みを作っていこうとも思ったのですが、その時ですでに30代も後半だったので、それではあまりに時間がかるなと思い、医療系のコンサルティング会社に入社しました。

外科医のキャリアを捨ててコンサルティング会社に!?
全然違う業界だったと思うのですが、仕事内容としてはいかがでしたか?

学ぶことも多かったのですが、やはり人の家の庭を耕していても面白くないなってことに気づいてしまい…(苦笑)。

(苦笑)。

人にアドバイスをしているよりも自分でやった方が楽しいだろうな
↓
では、地域医療を良くするためにはどこから始めるのが良いのだろう?
↓
入り口としては在宅医療が最も良いのかな?
と考えて、現在のクリニックの開設に繋がっていきましたね。

なので、在宅医療には想い入れを持って取り組んではいますが、「在宅医療だけをやりたい」かと言えばズレるんです。
「地域の底上げ」をしていくことを目的として、在宅医療は一つの軸でしかなく、他にも必要な資源は自前で用意をしたり、すでに地域にある資源と繋げていったりしていたら、今の形になっていったという感じですね。

血管よ何処に! 「点滴が入らなかったらそれは俺の寿命だ」という、ある患者さん

在宅の現場で見てこられた患者さんの中で印象深かった方のエピソードを教えて下さい!

色々な方がいますが、クリニック開設当初にお受けした60代で食道がんの患者さんは忘れられないですね。
もう食べ物が全く喉を通らない状況にも関わらず、ご本人が胃ろうもCVポートも拒否されたんです。
ただ、すごく喉が乾くので点滴だけはして欲しいという希望があって、その管理のために毎日通い続けていました。

そのような状態の方なので、もう血管ないんですよね、手も足も。
ただ、ご本人は「点滴が入れられなくなったら、それはもう俺の寿命だ」っておっしゃるんです。
うちの看護師は半べそをかきながら「入らないとは言えない…」と言って訪問をしていました(苦笑)。
僕自身も最も時間がかかった時は1時間半近くかけて血管みつけた時もありました。

必死に探すしかないですね、それは(汗)。
ご家族の意向としてはどのような?

「主人がそう言っているのだから、主人の言う通りで良いです。点滴が入らなかったら終わりにして下さい。」
ってな感じでしたね。
こちらとしては「終わりにできねぇだろ」と(苦笑)。

その方と向き合っている時に感じたのが、「自分たちがその方の命を握っている瞬間」だったんです。
彼の死に対して強烈に向き合っている感覚を覚えました。

それは病院勤務時での死への向き合い方とはまた違った、ということですか?

そうですね。
勤務医の頃は、仮にいま自分が担当をしていても、病院には他にも担当をしてくれる先生もいるし、その後ろには院長もいるし、といった意識がどこかあったのだと思います。

そのご利用者さんの最期はどのような形で?

この方、最期まで自分でトイレに行っていたのですが、トイレに座った拍子で、ふっと意識が落ちてしまい、そのままお亡くなりになりました。
血圧が一気に下がったのだと思います。

結果的に、2ヶ月ほどのお付き合いだったのですが、自分の死期を悟りながら、最後まで僕らへの気遣いも忘れなかった、とても立派な方でしたね。

そうなのですね。
ちなみに点滴は最期まで……?

入れ続けましたよ!
最初のうちは「留置も嫌だ」と言っていたのですが、僕たちが困っているのをみて「留置してもいいよ」と折れて頂きました(苦笑)。

高齢の患者さんが、在宅を選択するしかないある複雑な事情とは…?

先程のお話の中で「地域の底上げ」といったことを口にされていましたが、
実際にこちらのグループでは、在宅医療以外にも『障害者就労移行支援事業』や『街の保健室』、『健康相談室』といったものも取り組まれていますね。
そのような事業展開は立ち上げ当初から構想をされていたのですか??

どちらかといえば、このエリアの特性と向き合っていったら自然とそうなっていったという感じです。
神奈川県川崎市って7つの区があるのですが、この多摩地区って、下から2番目の低所得エリアなんです。
なので、在宅を選択される方の中には「お金がないから施設に入れない」といった理由の方がいて、そういった『在宅難民』といっても過言ではない方が多いエリアなんですね。

例えば、市営団地や県営団地に住んでいるおじいちゃん・おばちゃんがいて、引きこもりの息子さんも一緒の家に暮らしている。
もし、おじいちゃんやおばあちゃんが施設に入ってしまい、住居者の年齢が下がると家賃が上がってしまうので、引きこもりの息子さんは暮らせなくなってしまうんです。

そうなると在宅医療だけの問題ではないんですよね。
入院をする必要があるけど入院できない事情を抱えた患者さんがいて、その患者さんと密接に関わっているご家族がいる。
これは医療的な関わりだけではなく、地域全体のヘルスケアをもっともっと押し上げていかないとどうにもならないなと…(汗)。

「年金受給があるので、どんな形でも良いから延命をさせて欲しい」といった希望をされるご家族のケースに通ずるものを感じますね。

まさにそうですね。
似たようなケースはたくさん見てきました。

僕はこのクリニックを立ち上げた時から一貫して「多摩地区」にこだわり続けていて、別エリアに事業を広げていくことは一切考えていないんですね。
その地域に住む患者さんに本当に向き合っていこうと考えると、その方のご家族や家族環境にも向き合っていく必要性に迫られますし、その必要性に答えるためには一つの地域にフォーカスして資源を集中させていくしかないんです。

さらに付け加えると、例えば、訪問診療や訪問看護といった一つ一つのサービスを最適化していっても、それが地域全体の最適化にはならないこともわかってきました。
個の最適化を足し合わせても結果的に全体の最適化に届かなくて、多方面の資源をつなぎ合わせたうえでの全体最適化をはかっていく必要があると考えています。

僕はこれを
『まるごと地域クラスター構想』
と呼んでいて、うちの法人では地域内でそういった枠組みをキチッとつくっていくことを目標としています。

素晴らしいですね…!
インタビュー冒頭にも似たような話はしましたが、
在宅医療に注力をしている地区って日本国内でもいくつかありながら、そういった思想のもと医療・介護・福祉での一気通貫のサービス提供をしている法人って、本当に聞かないですよね?

いやぁ……、なかなか無いと思いますよ。
正直、収益化までかなり時間のかかるモデルなので(苦笑)。
だから、まずはうちが多摩地区という人口30万人程度の限られたエリアで成功モデルをつくって、それが日本各地の他のエリアにも広がっていってくれると嬉しいな、と思っています。

本日はありがとうございました!
取材を終えて

神奈川県多摩地区。多摩川を挟んだ東京と神奈川の県境に位置するこのエリアを拠点として、多数の医療・介護・福祉サービスを展開する『医療法人メディカルクラスタ』。
在宅医療の現場において切っても切り離すことができない、介護の問題、家族の問題、金銭面の問題 等々に明確な課題感とビジョンを持って取り組まれている、日本でも数少ない(他にどれだけあるのだろう?)医療法人となります。
こちらを検討される方には「在宅医療」や「訪問看護」に限定した形ではなく、広く「地域全体」を支えていくための取り組みに関心を持った方の方がよりやり甲斐を感じられるのだろうなと強く思いました。
(おそらく)日本初になるであろう『まるごと地域クラスター構想』の実現に向かって、一緒に走り抜けてみませんか?
取材・文章:一和多義隆
事業所情報

| 事業所名 | たまふれあい訪問看護ステーション |
|---|---|
| 運営会社 | 医療法人メディカルクラスタ |
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区枡形2-1-17-1F |
| 最寄り駅 | 小田急線「向ヶ丘遊園」駅 徒歩9分 |
| 在籍人数 | 看護師10名(常勤6名・非常勤4名)、理学療法士4名(常勤4名)、作業療法士1名(常勤1名)、言語聴覚士1名(常勤1名) |
| 従業員の平均年齢 | 20~60代のメンバーが在籍 |
| ステーション詳細 | » より詳細なステーション情報を見る |






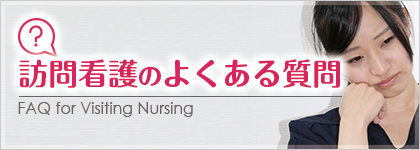
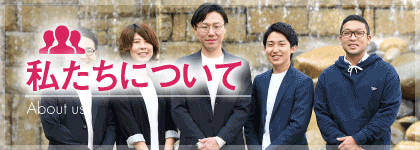
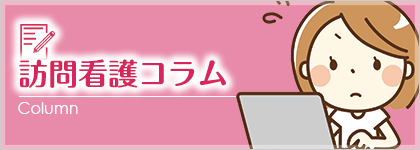

本日は、川崎市多摩区で往診クリニック・訪問看護ステーション・看護小規模多機能型居宅介護(以下、看多機)・就労移行支援 等といった、
医療・介護・福祉の総合ヘルスケアサービスを提供する『たまふれあいグループ』の理事長であり医師でもある、鈴木先生にインタビューをいたします。
よろしくお願いします!